50代派遣社員Eの職業紹介シリーズです!
新卒でレストランチェーンの会社に就職したのが1990年代前半のこと。
そう、バブル景気という日本を覆った大きな波が幻のように引いていった時代です。
そんな中、若き日のEは就活もテキトーで、入社1年目も三軒茶屋のゆる~い店舗で完全にバイト気分で過ごしたのでした。
しかしある時、店舗異動によって潮目が変わったのでした。
今回は二年目に異動した新宿の店舗で、Eがいかに店長候補として性根をたたき直され、さんざんな目に遭いながらも成長を遂げたのかについて語ります。
前回の記事です。
二年目の店舗異動
予期していたこととはいえ、それは突然訪れました。
新卒1年目のEが三軒茶屋の店舗で、若い従業員たちと和気あいあいと日々を過ごしていたある日、店長の呼び出しを受けます。
そこで告げられたのはそう、二年目の異動です。
異動は突然に
外食産業ならずとも、数多くの店舗や拠点を持つ会社なら頻繁な異動は珍しくないでしょう。引っ越しを伴う遠隔地への異動もよくあることです。
例にもれず、Eの会社も大卒営業社員は二年目を迎えると異動がありました。
店長に異動を告げられた翌日には本社に辞令を受けに行きます。遠隔地への異動でない限り辞令は容赦なく翌日です。
その日の仕事終わりには、急遽Eの送別会です。
出勤していた従業員ほとんどが三軒茶屋の行きつけの居酒屋に集ってくれました。
Eはたくさんの友人との別れは寂しくもありましたが、そろそろかなと予期していたし、新しい店舗で働く期待に胸を膨らせてもいました。
移動先はどこ?
本社で辞令。
それは朝イチで行われるため、普段よりだいぶ早い出勤です。
社長から直接辞令の紙を手渡されます。
Eの新たな配属先はそう、新宿の大規模店舗でした。
そう、就活中のOB訪問、そして前前の入社式でも訪れた、あの映画『ゴッドファーザー』のマーロン・ブランド扮するドン・コルレオーネのような貫禄ありすぎの店長がいる店です。
始めてコルレオーネ店長に会ったOB訪問以来、ぜひ彼の下で働いてみたいと思っていて、それが早くも二年目で実現することとなりました!
映画『ゴッドファザー』マーロン・ブランド扮するドン・コルレオーネ。
ひげがなければこの外見も貫禄も新宿の店長そっくり。
同期たちもそれぞれ新たな勤務地に異動です。
ちなみに入社当時8人いた大卒のEの同期は、この時点で2人が退職して残るは6人です。
新宿の店舗に初出勤
辞令を受け取ったその足で、というか電車で、それぞれの配属先へ。
新宿駅で降り、ビルの複数のフロアに広大な床面積をたたえる大規模店舗に到着。
何度も訪れている店舗ですが、裏方を見るのは初めて。
と、この日コルレオーネ店長はなぜか一日不在で挨拶できず。
Eが到着した時間がランチタイムの直前。
ほぼ全ての店舗がそうでしたが、ランチタイムは戦場のような大忙し。
二年目のEは挨拶もそこそこに制服に着替えて、店の構造も席番号もわからないながら接客作業を手伝います。
この大規模店舗には副店長が2人、マネージャーが3人と役職者は多数いるはずなんですが、この時なぜか副店長も2人とも不在。残ったマネージャー達もその日は昼から繁忙で忙しそう。恐らく宴会の予約が多数あり。
急に異動でやってきたEの扱いに困ったのか、この日はディナータイムを前に帰るようにと言われました。
特に改まって紹介されるでもなく、店長や役職者と話すでもなく、消化不良の初日を終えます。
大規模店舗の洗礼
異動二日目、シフト通りに11時頃に出勤します。
この日は朝礼にコルレオーネ店長も登場し、改めてEが紹介されました。
その後に年配の副店長に、これまた改めて店内を案内されます。
複数階にまたがる店舗は従業員用のエレベーターや階段、更衣室や倉庫など、巨大なビルの中で複雑なな経路で結ばれ、移動するにも大変な店舗であることを知ります。
前の店舗でバリバリ活躍していたEも、店の指揮系統や各フロア間の連絡系統など様々な店舗事情を理解しなければなかなか充分な活躍はできそうにありません。
と、数日働いているとあることに気付きます。
なにやら周りのEへの視線や態度が厳しいように感じるのでした。
周りというのは料理人たち、主に料理長以下の上層部です。
ことあるごとに難癖をつけてきて、業務にも支障をきたします。
仕事上かかわりを持たないわけにはいかず、今でこそあの程度のパワハラなら軽く撃退できるものの、20代そこそこの、無敵のコミュ力も強靭なメンタルも確立していなかった、新卒二年目にはなかなかハードでした。
だいぶ後から知ったんですが料理人たち、特に料理長と数名の調理場の上層部からの冷たい視線の原因は「Eが異動初日に調理場に挨拶に来なかったから」だったようです。
が、初日は上の人もいないし店もあわただしく、早めに帰されて調理場に挨拶という状況でなかったことは確か。

挨拶って重要?
新宿の店舗の風土として、なにしろ社内屈指の大規模店舗であるからには料理長以下の上層部は大ベテラン、社内全体でもトップの地位にあります。
調理場内での上下関係が厳しいだけでなく、フロアで働く者は彼らの下に仕える臣下、とばかりの扱いを受けていたのでした。
要するに、配属初日に調理場に来て料理長以下調理場メンバーに臣下の礼を見せに来てほしかったわけですね。うぜぇ。
一方のE、新宿の店舗に配属されるまでの人生で、上下関係が(理不尽に)厳しい環境に身を置いたことが一度もありませんでした。
挨拶についても重要視したことがなく、今でも職場であまり挨拶しません。日常的に業務でかかわる人や挨拶した方が得と判断している人だけです。もちろん向こうから挨拶してきた人には返します。
年上だったり、入社が自分より早いとか、調理場のメンバーからといって、相手を特別に丁寧に扱うというのは意味が分かりません。
挨拶は、したい相手になら自然に言葉が出てくるし、そうでなければ普通にスルーが基本です。
もちろん日本社会全体に挨拶重視の風潮があることは知っています。
しかし実際、それほど挨拶を重視しなくても成り立っている社会もあります。
フィリピンはセブ出身のEの妻と娘は、朝起きて顔を合わせても「おはよう」などの朝の挨拶をしません。現在セブに住んでいるお兄ちゃん二人も同じです。
Eは純日本人として習慣なので家族に対しては自然に「おはよう」とか「Good morning」の言葉が出てくるし、Eが挨拶すれば返ってきますが、そうでなければフィリピンの家族に挨拶は発生しません。
Eにはそういった社会の方が合っていると自覚してもいます。

要するに料理人たちは上下関係を重視する人たちであって、自分たちが格上で二年目の大卒社員は格下、という認識のもとに、挨拶に来なかったEを批判しているわけです。
そういった意味不明の上下関係になじめなかったEは、そのことによるマイナスを受け入れるしかないと、割り切っていたのでした。
が、そんなEの態度は後に、店長によって叩き直されます。
E自身も自力で変えられない以上、損得を考えればこの「上下関係が厳しい環境」を受け入れるしかない、と割り切るようになります。
そして、対調理場対策として「相手が自分にとってほしい態度」を見極め、「ここで仕事をしやすい状況を作る」という得を取るための行動を取り、半年もすると料理人、特に最もEにブチ切れていた料理長に気に入られるようにさえなるのでした。
要するに『目的のためには自分を殺して周りに合わせて得を取る」という一般的に大人がやっている処世術をここでようやく覚えたわけです。
これ、すごい成長じゃないですか?
にほんブログ村
憧れのコルレオーネ店長
配属からしばらくは、アルバイトと大して変わらない日常作業をこなしながら、店の仕組みを理解していきます。
店長から呼び出されるのは二日後のことでした。
一緒に呼び出されたのは高卒5年目のオオハシさん。
Eの異動と同時期に高卒のマネージャークラスの異動があり、新宿に元いたマネージャーと入れ替わりでやってきたのでした。
閉店後の客席でEとオオハシさんに、店長の故郷である長州藩の幕末の志士になぞらえて、これから店長を目指す上での心構えについての訓示を与えるのでした。
店長は歴史好きで、ことあるごとに歴史上の、特に幕末の志士を引き合いに出しては部下に訓示を垂れます。
「お前はよ、○○藩の出身だろ。○○藩と言えば○○(歴史上の人物)はな…」といった具合に。
店長は恰幅もよく、ともすると外見からは威圧感も感じさせますが、接してみると実に気さく。
おやじギャグもボケも連発するので、部下たちも慣れてくれば平気でツッコミを入れられます。
数か月後にはEを含めた同期全員は一斉にマネージャーになります。
そのころになるとその年の大卒新入社員のタニやんも加わり、仕事後に毎晩のように店長に連れられて居酒屋などで飲み歩くようになります。

そう、三軒茶屋での新入社員時代のEは飲みに行くといえば、バイトの大学生たちでした。
それが二年目の新宿では、バイトのメンバーと飲むことはほとんどなくなります。
常に飲み歩いていたのは店長以下、店の幹部クラスや若手の店長候補。ごくたまにバイトのリーダー格、という風に変わったのでした。
これも完全バイト気分だった新入社員時代から、少しは成長したといってもいいんではないでしょうか~。
店長は一目でEが、大学時代を能天気に過ごし、いまだに完全バイト気分で、世の中を知らない、上下関係が厳しい環境での生きる術さえ知らない、幼児性の抜けない若造であることを見抜いたわけです(ま、当時のEを見れば一目瞭然ですが)。
恐らく店長自身、若手を育てることが喜びでもあったのでしょうが、Eを始め二十歳そこそこの店長候補たちにこの会社で生き残っていく術を、ややくどい、また同じこと言ってる、などと思われつつも熱心な指導を受けるのでした。
しかし、店長の若手指導にはひとつ、大きく欠けているものがありました。
それは、精神的な指導がほとんどで、店舗の運営や経営といった実務的な内容がなかったということです。
店長になるには、店のオペレーション、販促営業活動、サービス品質の維持、フロアの人員確保、育成、など覚えるべきことは多岐にわたります。
が、この二年目に至ってもそういった店舗経営実務を身に着けることができていなかったのです。
Eが店長になるにあたっての実務的な指導を受け、経験を積むのは1年後、Eの入社3年目に新宿の店舗を取り巻く環境が大きく変わった時でした。
が、これについては後日語ります。

日本最大の繁華街、新宿。
当時はゴジラもドンキホーテもありませんでした。
前店舗との違い
社内でも大規模な店舗とされる1年目の三軒茶屋と二年目の新宿。
二つの店舗は同じ会社であるにもかかわらず、様々な面で違いがありました。
まとめるとこうです。
| 一年目(三軒茶屋) | 二年目(新宿) | |
| 店舗規模 | ビルのひとフロア | ビルの複数フロア |
| 客席 | 一般席、個室あり 150人収容の宴会場 | 一般席、個室も多数 300人収容の宴会場 |
| 売上 | 一日最大200万円 | 一日最大400万円 |
| 立地・ 繁忙度 | 三軒茶屋駅至近 超繁忙 | 新宿の超繁華街 繁忙度は日本屈指 |
| フロア 従業員 | 社員4~6名 バイト・パート約40名 必要に応じて配膳会 | 社員約10名 バイト・パート約80名 必要に応じて配膳会 |
| 店舗の 雰囲気 | ゆるくてアットホーム | 全体に意識高め 料理場の緊張関係あり |
とまあ、とにかく忙しい店で週末は開店から客足が途切れることなく、待合いは常にいっぱい。
客層といえば、近隣商業施設の買い物客から、企業の宴会や冠婚葬祭と幅広く、結婚シーズンには披露宴も開かれます。
料理も千円台のランチから、ひとり数万円の高級料理まで多彩。
まさに二年目の社員が勉強するにはうってつけの店舗でした。
それまでバブル景気だったこともあり、大量の客を大量の従業員でさばく、という力業の経営で成り立っていたのでした。
しかしバブル景気の崩壊による業績低下と同時に店は、そして会社全体は変化を迫られます。
まとめ
このように、完全バイト気分で過ごしたEに変化が現れます。
実はE自身、三軒茶屋で1年を過ごし、近い将来店長になるために何も身に着けていないことに危機感を感じてもいました。
この二年目の店舗異動は成長のきっかけではあったものの、実務経験としてはまだまだ。
3年目、バブル崩壊で売上に大打撃を受けた新宿の店舗は本社に改革を迫られます。組織改革が断行され、Eはさらなる試練を受けることになります。
さて、Eはどんな試練を受け、店長になるべく成長するのでしょうか。
次回をお楽しみに!
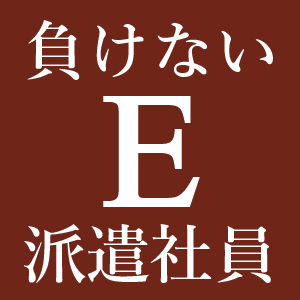




コメント